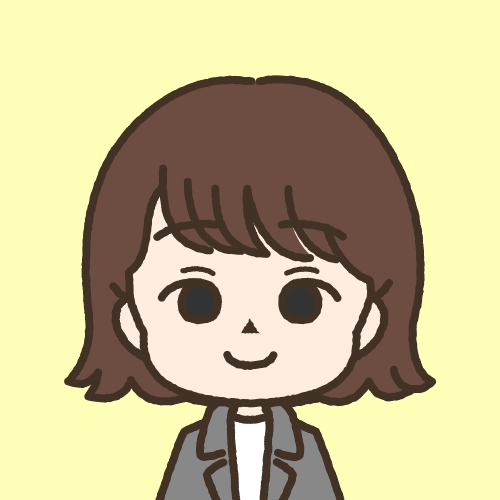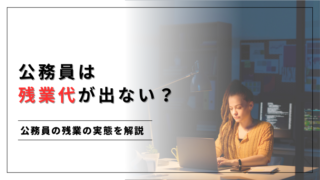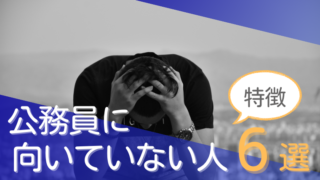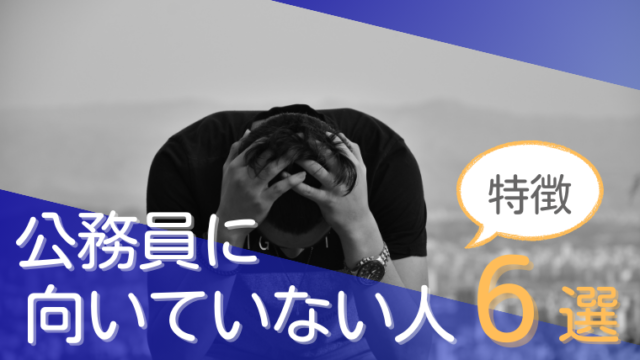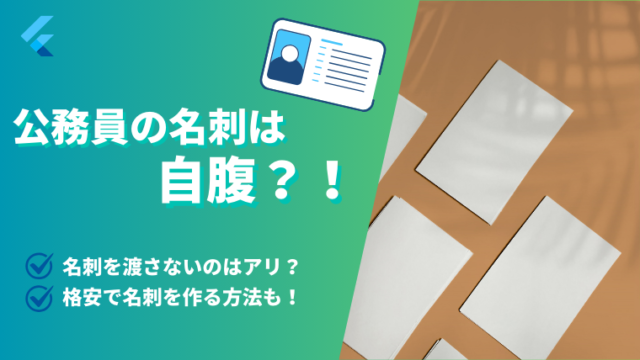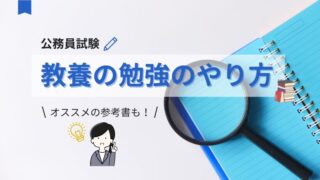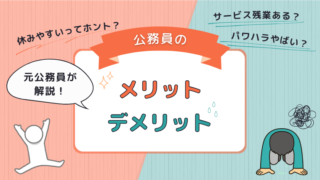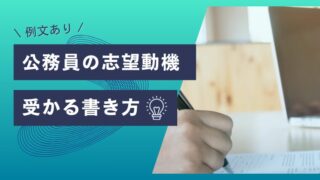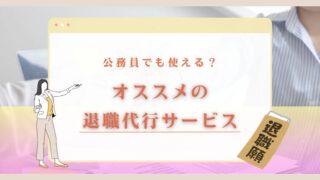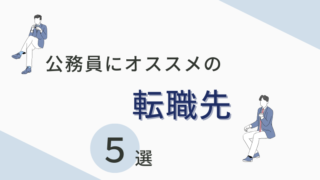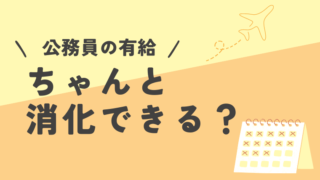こんにちは!元公務員の ろびんそん です。
安定した職業のイメージが強い公務員。
その一方で、長時間労働やハラスメントなどの悪いウワサも聞きますよね。
この記事では、公務員になるメリット・公務員のデメリットを元公務員目線で解説していきます。
- 公務員のメリット【3選】
- 「公務員になってよかった!」と思った瞬間
- 公務員のデメリット【3選】
- 公務員を退職した本当の理由
- 公務員に向いている人の特徴【3選】
この記事を書いたわたしは元地方公務員。
じっさいに公務員を10年ほど経験して感じた【本当のメリット】と【想定外だったデメリット】を超具体的に解説します。
この記事を読むことで、「自分は公務員になるべきなのか?民間にいくべきなのか?」が分かります!
公務員のメリット【3選】

「やっぱり公務員はすごい!」と感じた、公務員のメリットはコチラ↓↓
- 社会的信用の高さがトップクラス
- 年功序列で給料が上がりつづける
- 休暇制度が神レベルで整っている
それぞれ詳しく解説します。
メリット1:社会的信用の高さがトップクラス
1つ目のメリットは、社会的信用の高さがトップクラスであること。
安定した職業のイメージが強い公務員は、社会的信用がとても高く、
- 賃貸マンション、アパートの審査がサッと通る
- クレジットカードの審査も通りやすい
- 住宅ローンの金利が優遇される
- 住宅ローンの審査が通りやすい
このように、金融系や不動産系の審査で、公務員がいかに信用された職業かがわかります。
わたしも審査で困ったことはありませんでしたし、審査のスピードもものすごく速く進んだのを覚えています。
メリット2:年功序列で給料が上がりつづける
2つ目のメリットは、年功序列で給料が上がりつづけること。
公務員の給料は、表向きには人事評価が反映されることとなっていますが、じっさいは年齢や経験年数がもっとも影響します。

近年では、年功序列を廃止する民間企業も増えてきましたが、公務員の年功序列制はまだまだ堅いまま。
「能力で評価されない」という側面もありますが、歳さえ取れば給料が上がっていくのは、労働者にとっては大きなメリットですね。
メリット3:休暇制度が神レベルで整っている
3つ目のメリットは、休暇制度が神レベルで整っていること。
公務員の休暇は、年次休暇(民間企業でいう20日間の「有給休暇」)の他にも、たくさんの休暇があります。
- 年次休暇
- 病気休暇
- 不妊治療休暇
- 妊娠障害休暇
- 妊婦健診休暇
- 産前産後休暇(男性は「妻の出産休暇」)
- 子の看護休暇
- 短期介護休暇
- 夏季休暇
- 結婚休暇
種類がたくさんあるだけでなく、休暇が取りやすいのも特徴。
採用間もない頃は、「まわりが休みを取っていないと自分も休みづらい」と感じやすいですが、わたしが経験した職場では、
ろびんそん
上司もまわりの職員も休んでいるから、自分もたくさん休もう!
と思えたことが多かったです。
ヒマ部署にいた時には、1年間で30日以上の休暇を取ったこともありました。
民間企業に勤めている友人の話を聞くと、この休みやすさは【公務員ならでは】であることが分かります。
公務員になってよかった!と思った瞬間

公務員になって良かった!と思った瞬間は、あまり聞こえが良いことではありませんが、病気休暇を取って体調を整えられたことです。
公務員の休暇制度のなかに、病気やケガで療養が必要なときに取れる「病気休暇」という休暇があります。
詳しくは以下の記事で解説しております↓↓
病気休暇は、給料が100%保証された状態で3か月まで休むことができる休暇。
病気休暇が終わったあとに休職に切り替わっても、給料の80%が保証される期間があります。
私はメンタル系を理由に病気休暇を取ったので、何かと不安をかかえることが多かったのですが、
ろびんそん
休んでいる間も収入が保証されるから、療養に専念できる
と、収入面で過度に不安になることはなかったです。
メンタル系で体調を崩すと、回復に時間がかかります。
収入が保証された状態で、長期間にわたり休むことができたのは、本当に良かったと思いました。
なかなか民間企業では存在しない休暇制度なので、公務員が待遇面でいかに恵まれているか分かりますね。
公務員のデメリット【3選】


公務員を10年ほど続けて「これは耐えられない・・・」と思ったデメリットはコチラ↓↓
- 意外と残業が多い、サービス残業も・・・
- 古い慣習が残っている
- 市場価値を高めにくい
それぞれ詳しく解説していきます。
デメリット1:意外と残業が多い、サービス残業も
1つ目のデメリットは、意外と残業が多く、部署によってはサービス残業も強いられること。
公務員と聞くと「9時-5時」をイメージする人も多いですが、残業の多い世界です。
テレビでは、キャリア官僚の残業がよく取り上げられていますが、国家公務員の一般職でも、地方公務員でも残業はあります。


ただただ残業するのであればまだマシですが、職場によってはサービス残業を強いられるところも。
わたしも予算がカツカツの部署にいた時は、残業しても休日出勤しても、残業代は請求させてもらえませんでした。
上司からハッキリと「NO」と言われた訳ではありませんが、
みんな時間内に仕事を終わらせているんだから、あなたも時間内に終わらせられるようにしなさい。
と言われました。
(それが出来ないから相談しているんですよ・・・・・・)
まわりの職員に聞いてみると、「残業代を申請せずに残業したり、家に持ち帰って仕事をしている」とのこと。
ただ、サービス残業が当たり前の職場もあれば、残業代を申請してもOKな職場もあります。
そもそも、残業がまったくないヒマ部署もあったので、配属される部署によって大きく異なると思っておきましょう。
公務員の残業のリアルについては、以下の記事でくわしく解説しています↓↓
デメリット2:古い慣習が残っている
2つ目のデメリットは、古い慣習が残っていること。
公務員になってから驚いたことでもありますが、紙文化が根強く残っていたり、上下関係が厳しいあまりパワハラやセクハラが横行していました。


まずは紙文化。
公務員は書類仕事が多いので、仕方のないことではあります。
ですが、ITツールを活用して資料を確認・提出したりすることが当たり前の世代からすると、戸惑うことも多いです。
ろびんそん
資源と時間とお金のムダだなぁ・・・
とイライラしながら仕事をすることは、私にとって大きなストレスでした。
そして、紙文化以上にストレスだったのがハラスメント。
- 大勢の職員がいる場で怒鳴る
- 人格を否定する
- サービス残業の強要
- 必要な情報を共有しない
- 飲み会で手を握る・抱きつく
- プライベートなことを執拗に聞く
今思えば、とんでもない上司たちだった・・・と思えますが、当時はひたすら自分を責めていました。
ろびんそん
社会人になるって、こういうこと。すべて原因は自分にある。
今後はコンプラ意識も高まっていくことにより、ひどいハラスメントは減っていくと思います。
ですが、パワハラ・セクハラが当たり前の時代を生きてきた人はまだ現役なので、パタリとなくなることはありません。
前例踏襲かつ変化を嫌う公務員の世界では、民間企業よりも古い慣習が残りやすいです。
デメリット3:市場価値を高めにくい
3つ目のデメリットは、市場価値を高めにくいこと。
転職が当たり前になった昨今、じぶんの市場価値を高めていくことが重要になります。
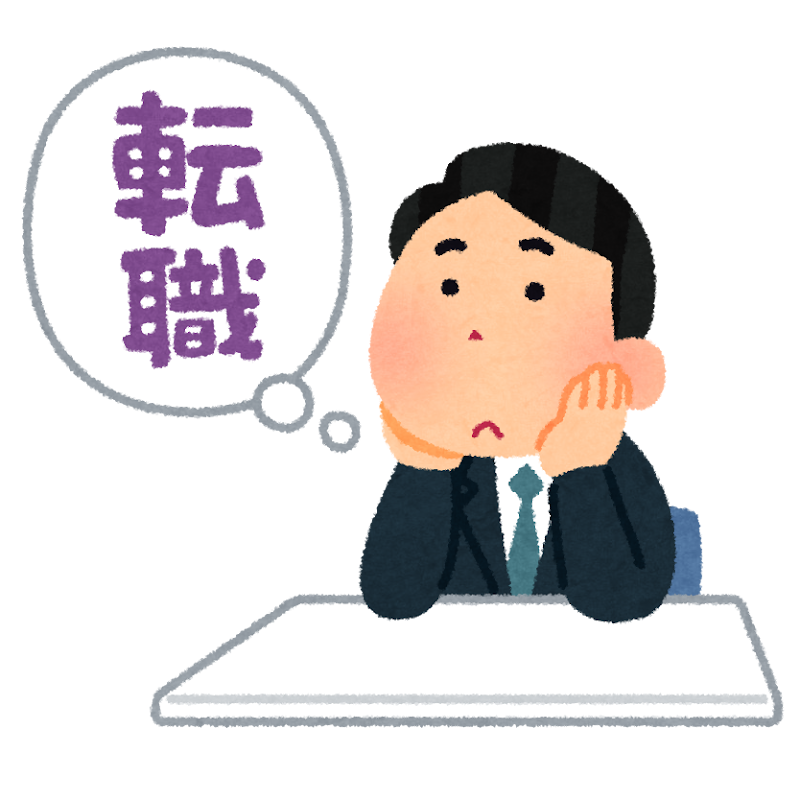
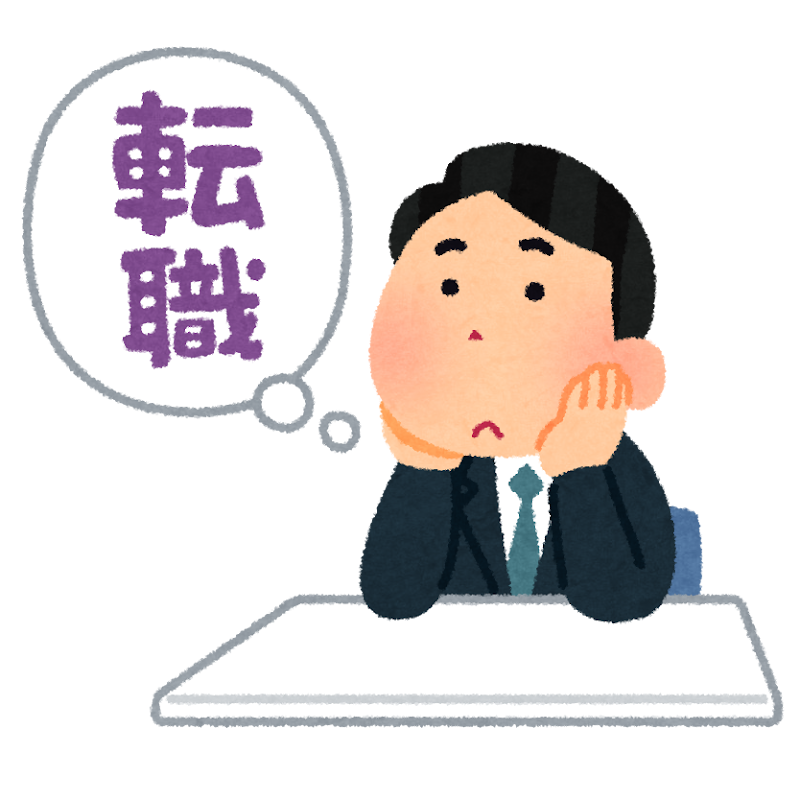
市場価値を高め、他の組織でも持っているスキルを活用していきたいところですが、転職市場では「公務員のスキルは公務員でしか通用しない」という雰囲気があります。
もちろん、元公務員であっても民間企業で活躍されている方がいらっしゃるのも事実。
ですが、一般的には、公務員を長く続けた人材の需要はかなり低いです。
わたしが公務員9年目あたりで転職活動をしたとき、なるべく職歴以外でアピールできることを面接で話しました。
20代前半のときの転職活動と比べて、そう簡単には内定は出ませんでした。
少しでも「公務員やめたい・・・・・・」と思ったことのある人は、早めに自分の市場価値を高めておきましょう。
市場価値を高める方法の一つとして、資格取得がオススメ。
公務員にオススメする資格を以下の記事で解説しておりますので、少しでも「公務員やめたい・・・・・・」と思ったことのある人は必見です。
公務員を退職した本当の理由
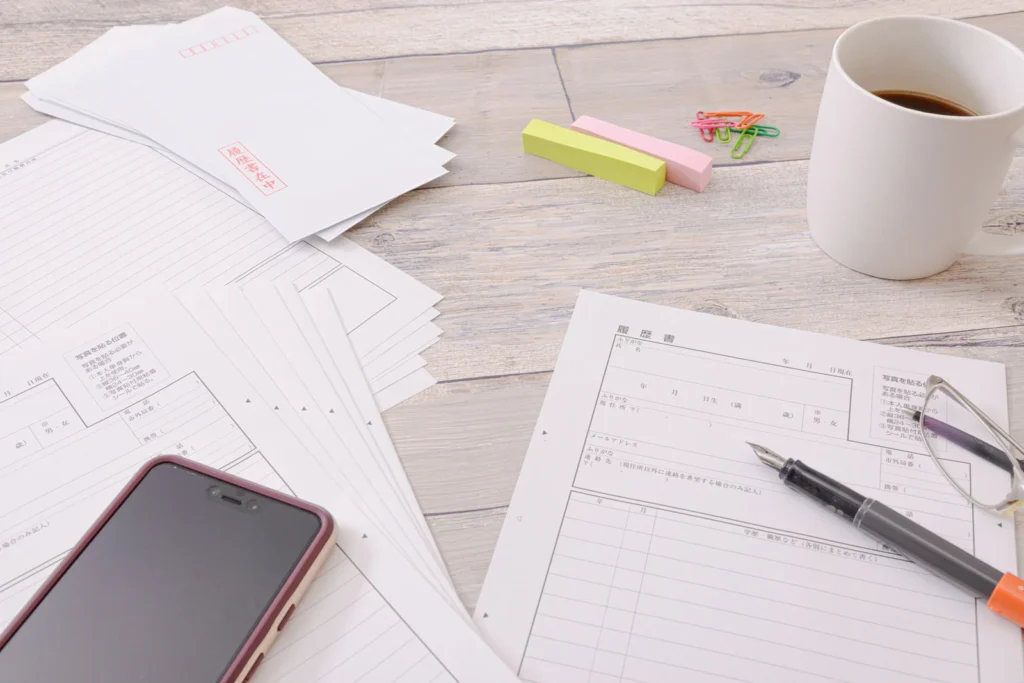
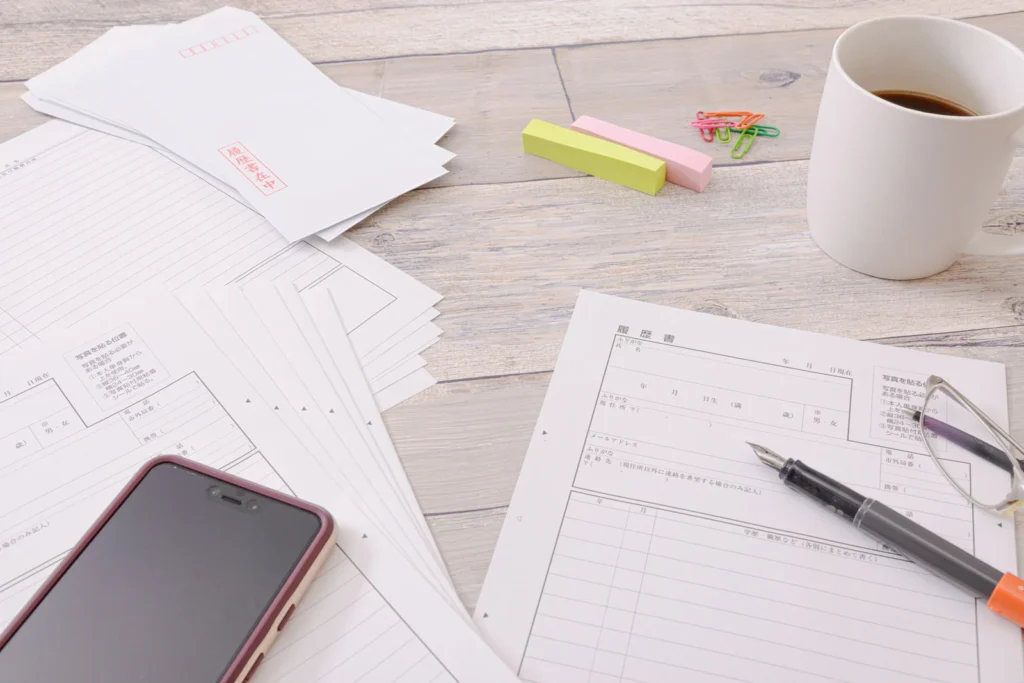
私は公務員を10年ほど続けましたが、その間に何度も転職活動をしてきました。
しかし20代のうちは、いただいた内定を蹴って、公務員を続ける選択を繰り返してきました。
公務員にしがみついてきた私ですが、30歳を過ぎたあたり、「真の安定とは何か?」をやっと理解することに・・・・・・。
どこへ行っても、自分なら大丈夫だ。
と、思えることが真の安定です。
「絶対に倒産しないから」「大きな組織だから」と言って、1つの組織に依存する人も多いですよね。
しかし、自分以外のものに依存して、何もかも委ねてしまうと、不安は増大するばかり。
公務員がクビになることはまずないですが、職場のストレスなどで体調を崩して職を失う危険性とは常に隣り合わせです。
公務員の地位を失ったときでも、「自分なら大丈夫だ」と思えるような知識・スキル・経験をもっておくことで、安定した人生を歩むことができます。
わたしは、30歳を過ぎてから「本当の安定した人生」を歩むために転職を決意しました。
公務員には安定志向のひとが多いです。
安定志向のあなただからこそ、「真の安定とは何か?」を考えてみてほしいです。
公務員に向いている人の特徴【3選】


以上をふまえて、公務員に向いているのはいったいどんな人なのか?を解説していきます。
- 公務員の仕事でやりたいことがある人
- 子育てに重きをおきたいと思っている人
- ジェネラリストでいたい人
それぞれ詳しく解説していきます。
特徴1:公務員の仕事でやりたいことがある人
公務員に向いている人の特徴1つ目は、公務員の仕事でやりたいことがある人です。
「安定しているから」と言って公務員になる人が多いですが、具体的にやりたい仕事があって公務員になる人もいます。
福祉系の部署の窓口で、住民対応をしたい!
防災系の部署で、住民の安全を守る仕事がしたい!
公務員の仕事でやりたいことがある人は、やりがいを持って仕事をすることができますし、大きく成長することもできます。
どんなに優秀な職員でも、イヤイヤ仕事をやっている人は、やりがいを持って仕事をする人には敵いません。
公務員でやりたい仕事がある人は、迷わず公務員を目指しましょう!
特徴2:子育てに重きをおきたいと思っている人
公務員に向いている人の特徴2つ目は、子育てに重きをおきたいと思っている人です。
公務員の休暇制度には、妊娠・出産・子育てをする人が取れる休暇がたくさんあります。


休暇制度が整っているだけでなく、じっさいに休暇を取る人が多いのもポイント。
最近では、就職して1年目のときに結婚して、2年目に出産して早々に育休を取る職員が増えている印象です。
就職してすぐに結婚・妊娠・出産をすることに否定的な人もいますが、わたしは「とても賢い選択だな」と感じますね。
子育てしている人は、休暇以外のところでも何かと優遇されます。
(災害対応系の仕事の一部が免除されたりなど)
子育てに専念したいけど、収入がなくなるのは心配・・・・・・と感じる人は、公務員という選択肢を考えてみましょう。
特徴3:ジェネラリストでいたい人
公務員に向いている人の特徴3つ目は、ジェネラリスト(=広く浅く経験したい人)でいたいと思っている人です。
公務員は3~4年のスパンで異動(短い人は半年で異動する場合もあり)があります。
やっと仕事を覚えてきた!
仕事がおもしろくなってくるのはこれから!
などと思ったタイミングで、異動があるイメージ。
せっかく仕事を覚えたのに、異動するとまた1から新しい仕事を覚えなければいけません。
1つの分野を極めたい人(スペシャリスト)にとっては、もどかしいですが、広く浅く仕事がしたい人(ジェネラリスト)にとっては、新鮮に感じます。
スペシャリストというよりは、ジェネラリストかな・・・・・・と自分で思う人は、公務員という選択肢もアリですね。
以上、公務員が向いている人の特徴を解説しました。
反対に、公務員が向いていない人の特徴を以下の記事で解説しております↓↓
「本当に自分は公務員を目指しても大丈夫なのか・・・・・・?」と少しでも不安がある方は必見です。
まとめ
公務員のメリットとデメリット、私が公務員を退職した理由、公務員に向いている人の特徴について解説しました。
- 公務員のメリット:社会的信用の高さ、年功序列で給料UP、充実した休暇制度
- 公務員のデメリット:サービス残業の多さ、古い慣習、市場価値を高めにくい
- 「真の安定とは何か?」を考えた末、公務員を退職
- 公務員時代に病気休暇でメンタル&体調を整えられたのは、本当に良かった
- 公務員に向いている人:公務員の仕事でやりたいことがある、子育てに重きを置きたい、ジェネラリストでいたい人
公務員がいいのか?民間企業にいった方がいいのか?
悩み出してしまうとキリがありませんが、自分の気持ちと向き合ったり、しっかり自己分析することが大切。
どのような結論を出しても、悩んだ末の結論であれば、大きく後悔することは無いですよ◎
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
.png)